2006/04/07 Friday
「ジェレイントとエニド」の7作目をアップしました('My vigor is not lost.')。道中度々襲われることとなる二人。エニドは命に背いて夫に危険を知らせ、ジェレイントは存分に力を発揮し敵を蹴散らします。しかし彼をやっかむ伯爵の大軍勢による襲撃を受け、最後には力尽きてしまうのです。
2006/04/07 Friday
「ジェレイントとエニド」の7作目をアップしました('My vigor is not lost.')。道中度々襲われることとなる二人。エニドは命に背いて夫に危険を知らせ、ジェレイントは存分に力を発揮し敵を蹴散らします。しかし彼をやっかむ伯爵の大軍勢による襲撃を受け、最後には力尽きてしまうのです。
2006/04/03 Monday
友人に電話をかけようと住所録を開いてみたところ、見事に真っ白。「まさか消えた?」先日バックアップをとったばかりだったのでそちらを開いてみても同じく真っ白。「???」かなりあせりました。
結論から言えば大丈夫だったんですけどね。古い友人などの連絡先は5年以上前のはがきスタジオというソフトに登録したままずーっと使っているのですが、どうもこれの住所録ファイル、場所を動かしてしまうと開けないみたいです。先日バックアップついでに保管場所も整理しようってんで移動していたのでした。はー心臓に悪い。
2006/04/01 Saturday
以前の記事でOperaでの表示に対する愚痴を書いたのですが、最新バージョンなら大丈夫と教えて頂きました(ありがとうございました)。早速OperaのサイトからDLしてインストール。旧バージョンと並存OKでしたので、折角だからちょっと比較してみました。
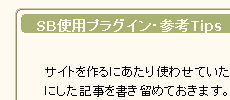
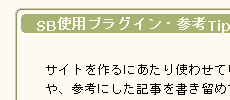
タイトル文字の高さと、字間に注目。フォントを「Verdana」にすると欧文フォントと和文フォントで段差が出来たり、字間がやたら開いてしまう・・・というのが旧バージョンでの不満の種だったのですが(気にしだすと非常に気になるのです)、上手く解消されているようです。こりゃめでたい。
他にも馬鹿でかい広告バナーがなくなったり、コテコテだったデザインが随分すっきりしたものになるなど、個人的に気に入らなかった部分もだいぶ様変わりしているようです。これだったらなかなか良いかも。
2006/03/31 Friday
2006/03/29 Wednesday
同名の本を2冊。
忍足欣四郎訳:岩波文庫
古英語による英雄叙事詩で、8世紀頃に成立したものとされています。物語はおおまかに二つに分かれ、前半部では若き日の主人公の怪物退治が、後半部では老いた主人公が竜を退治するも自らも力尽きるくだりが歌われています。
硬派というか大変骨太な詩で、ヒロインの類などは全く登場しませんし、主人公がうじうじ悩んだりすることも一切ありません。英雄ベーオウルフの行動のみが本筋として語られ、それらは大変勇ましいのですが、詩全体としては暗いトーンで覆われているような気がします。後半の竜退治では、トールキンの『ホビットの冒険』を思い出しました。宝の山を守っている様子などそのまんまです。実際トールキンもこの作品を好んだようで、『ベーオウルフ』に関する論文も書いているそうです。
あとは物語そのものの面白さもさる事ながら、訳が非常に素晴らしいと思いました。重厚な文体でありながら、とても読みやすい。注釈や作品についての解説も読み応えのあるもので、いい本よんだな~という気にさせられました。
ローズマリ・サトクリフ著:井辻朱美訳:原書房
実は読んだのはこちらが先。こちらは散文形式ですが、脇筋が削除されたり補完的な描写がある他は原作と全く同じ内容です。文字のサイズと字間が異様に大きいものの、お子様向けの文体というわけではなく、むしろ古語調を意識したいかめしい言い回しが多用されています。ちょっと読みづらかった気も。それでも1時間余りで読めてしまったのですけど、話は過不足なく書かれているので筋を知るのには充分だと思います。
2006/03/25 Saturday
どうも特定の記事にスパムが寄せられる様なので、それらの記事だけ「コメントを受け付けない」設定にしてみたら、頂いたコメントも表示されなくなってしまうんですね。コメントくださった方、ごめんなさい。コメントそのものはちゃんと残っておりますので。
うーん、どうしたものか。
2006/03/21 Tuesday
1963年、ドン・チャフィー監督。
ギリシア神話をベースとした作品でゼウスをはじめとする神々なんかも登場しますが、普通に冒険ものとして観ても十分に楽しめます。主人公のイアソン(ジェイソン)が伝説の金羊毛を求め、仲間を集めて冒険に出るというお話。
特撮映画の傑作として有名だそうで、確かに素晴らしい出来です。今時のCG全開なビジュアルを想像してはいけませんが、下手にCGを乱発して興醒めしてしまう類のものよりよほど見ごたえがあります。序盤は割と地味で、展開とあいまって途中少々退屈してしまったのですけど、中盤以降話が盛り上がってくるのにあわせて特撮のレベルもアップ、クライマックスのスケルトン部隊との戦闘シーンには度肝を抜かれました。
出演陣も主人公の人は物凄~く地味ですが、ゼウスとかヘラクレスとか、良い味を出していたと思います。ちょっと間抜けな感じが素敵。一応のヒロインであるメディア役の人も綺麗でした。このメディアという女性、神話では非常に恐ろしいエピソードの持ち主です。イアソン達と共に船で逃げる際、父王等追っ手から逃れる為、あろうことか弟を殺して切り刻み、海にばら撒くという。さすがに映画ではごく当り障りのない終わり方になっていましたけどね。
2006/03/20 Monday
ここ数日、コメントスパムが急増してます。SereneBachは拒否IPの設定ができるんですけど、コメント2、3個毎にIPも変わっているようでIPで拒否しても根本的な解決にはなりそうにありません。とりあえず非公開に設定してちまちま手動で削除してるんですが、記事のアクセス数にも反映されてないみたいだし、一体どういうカラクリなんだか。
2006/03/19 Sunday
昨日、首だか肩だかの筋をちがえてしまいました。朝から妙に肩が凝るので腕を思い切り伸ばしてたら、「ピキッ」「ウッ!」・・・と。
首が動かなくなってしまいもう大変。うがいは出来ず目薬もさせず、昨夜は全く寝返りをうてずに半ば金縛り状態。今日は墓参りをパスしたものの机に向かってもさっぱりで、録画しっ放しだった番組を見たりとかDVDに焼いたりとか、グダグダでも出来るような事ばかりしておりました。
筋をおかしくするのは初めてではないのですけど、これほどひどいのは今までなかった気がする。バ○テリン塗ってすこ~し楽にはなったんですが・・・歳かのう。
2006/03/17 Friday
「ジェレイントとエニド」の6作目をアップしました('Not at my side.')。ジェレイントはエニドの涙を、彼女が自分以外の男に想いを寄せているものと誤解してしまいます。
「私が本当に力を失ってしまったのか、その目で確かめるといい」
こうして二人は旅に出ますが、ジェレイントはエニドに自分の前を行き、一言も話し掛けてはならぬと命じます。
以下、蛇足。