2008/03/11 Tuesday
Home/Blog/
2008/03/05 Wednesday
2008/03/04 Tuesday
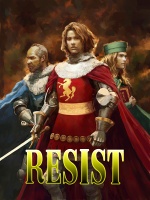
お仕事情報です。
同人ゲームサークル「トロッコ」様が現在製作中のゲーム「レジスト」において、タイトルイラストおよびゲーム中のキャラクター絵・イベント絵を描かせていただいてます。
「レジスト」は西洋中世を舞台としたシミュレーションゲームで、国づくりを進めながら最終的に敵領主を倒すのが目的です。中世の世風を感じさせる要素を随所に取り入れているとの由。今夏の完成に向けて開発状況はトロッコ様のサイトで逐次更新されていますので詳しくはそちらをご覧ください。40点弱のキャラクター、10点余りのイベント絵を描かせていただき、個人的にも完成を楽しみにしております。
2008/03/01 Saturday
三つの短編が収められています。それぞれ舞台は異なりますがいずれにおいても二人の主要人物間の友情が描かれ、それぞれ小道具として冠が登場します。中でも第一話の「族長の娘―ヒースの花冠」が好きです。少女と捕虜の少年との、友情とも恋心ともつかない微妙な心の動きがよく描かれていると思いました。
本書も先の『ケルト神話 炎の戦士クーフリン』同様ヴィクター・アンブラスが挿画を手がけています。こちらもまた大変素晴らしいものです。
- 『三つの冠の物語―ヒース、樫、オリーブ』
- ローズマリー・サトクリフ著/山本史郎訳
- 原書房
2008/02/24 Sunday
ケルト神話の英雄クーフリンの生涯を描いた物語。クーフリンは太陽神を父に持つ、アイルランド一と謳われた戦士です。
力強く、激しく、そして悲壮感の漂う物語です。クーフリンの物語を読むのは本書がほぼ初めてで(ブルフィンチの『中世騎士物語』には「アイルランドの勇士キュクレイン」として短いながらも収録されてます)、どの程度著者による脚色がなされているのかわかりませんが(あとがきによれば大変忠実に再話しているとの由)、非常にドラマチックでもあります。
エピソードの中で興味深かったのはアイルランドの英雄の称号を巡る争いの話。巨人が自分の首を切らせ、生きていたら切った相手に同じ事をさせろと要求するのですが、この逸話は『サー・ガウェインと緑の騎士』や円卓の騎士、腕萎えのカラドクのものとほぼそっくり同じです。きっと原形があってそれが各々に取り込まれているのでしょうね。それと序文において、アングロ・サクソンの英雄ベーオウルフと比較している部分も興味深く読みました。
あと個人的に特筆しておきたいのはVictor Ambrus(ヴィクター・アンブラス?)によるペン画の挿絵の素晴らしさです。全く知らなかった名前ですが、点と線・塗潰した面の織り成すリズム感や最低限の対象物を描くだけで最大限に物語を表現しているところなど、本当に凄いと思いました。
- 『ケルト神話 炎の戦士クーフリン (ケルト神話) 』
- ローズマリー・サトクリフ著/灰島かり訳
- ぽるぷ出版
2008/02/14 Thursday
世界のはてにあるという神秘の泉を求めて、小国の王子が冒険を繰り広げる物語。
謎に満ちた美しい女王や主人公を支える賢者、身分は低いものの気高い娘・・・などなど、現代のファンタジーではお馴染みともいえる様ざまなタイプの人物や要素が登場します。冒険を通して主人公が逞しく成長していくところなんかもそうですね。トールキンも影響を受けたんじゃないかな~と感じる部分が読んでいて多くあったのですが、解説によると実際そうみたいです。
個人的に興味深かったのは主人公の出会いと別れ、そして再会が多くの人物について印象深く描かれている点。物語の前半、別れの場面が印象的だと思って読んでいたところ、再会に転ずる物語後半は一層面白く、先を読みたくなるだけの勢いがありました。
ファンタジーの好きな方にはおすすめできる傑作だと思います。
- 『世界のはての泉(ウィリアム・モリス・コレクション) 』全2巻
- ウィリアム・モリス著/川端康雄・兼松誠一訳
- 晶文社
2008/02/11 Monday
ジョン・シンガー・サージェントは19世紀後半~20世紀前半にかけて活躍したアメリカの画家。実はかなり最近まで知りませんでした・・・
大胆な光の捉え方や確かながらも硬くなり過ぎない造形等、とんでもない上手さを持った大変素晴らしい画家と思うのですが、日本での受容度は今ひとつのような・・・肖像画家として一段低く見られてしまっているとか? 最近まで知らなかったからって自分を基準にしちゃいけませんかね(汗 ともかく単に滅茶苦茶上手いというだけではなく、人物の眼に深みがあってとても印象的だと思うんです。
本書も先のウォーターハウス同様のポケットサイズです。こちらはもう少し大きいサイズで見たい気もしますね。
2008/02/11 Monday
最も好きな画家のひとりであるウォーターハウスの画集です。どこが好きかと言ったらやはり彼の描く女性達の上品でやや翳りのある顔つき。描き過ぎないとこも好きです。大抵ざっくりした部分が残ってる。
この本は小さなポケットサイズですが、絵によっては全体図と部分のアップを載せてあったりして充分に楽しめます。ちなみに特に好きな絵は「The Lady Clare」「The Shrine」など。本書にも収録されています。
2008/02/10 Sunday
一応子供向けの本ということで、ユーサーとイグレインが「普通に」結婚した事になっていたりしますが、訳者の方が解説で述べられている通り硬質な文体で抵抗なく読めました。内容的にはアーサー王と円卓の騎士の活躍を追ったもので、なかでも聖杯の由来と探求について多くの紙数が割かれています。ちくま文庫版の『アーサー王の死』では削られていた部分でもあり、面白く読みました。佐竹美保さんによる挿絵も大変素敵なものです。
- 『アーサー王物語 (偕成社文庫) 』
- ジェイムズ・ノウルズ著/金原瑞人編訳
- 偕成社
2008/02/03 Sunday








